ヒアリング調査・インタビュー調査(デプスインタビュー調査)は、ひとりの調査対象者に1対1の面談形式でインタビューを行い、1つの事柄について深掘りする調査です。
「なぜそう思うのか、そう思う理由」「どういう行動・評価・判断をしているのかを詳しく」など、アンケート調査結果の数値ではわからない「なぜ」や「どのように」といった意見や行動についての情報を詳しく収集したり、更に話を掘り下げることで深層心理や感情の分析までできる調査手法です。
人の行動は理屈だけでは説明できず、そこには好き嫌い、後ろめたさなど様々な感情が入っています。行動の裏にあるその人の「感情」の動きに気づくにはアンケート調査では限界があり、ヒアリング調査・インタビュー調査が適しています。
ヒアリング調査・インタビュー調査の実施場所は落ち着いて話を伺える場所(会議室など)や、屋外での行動に関する調査なら屋外で(例えばスポーツに関する調査など)、お宅に訪問して話を聞いた方がよい場合はお宅に訪問、など調査で収集する情報が最上・最適になる場所を設定します。コロナ以降はZoomなどでのオンライン調査も増えてきています。
お宅訪問の例でいえば、バスルームやキッチン・トイレといった家の設備の話や、洗濯の仕方、食事の作り方、家での過ごし方など、実際に拝見しながらのほうが話の内容に間違いがなく、設置場所の観察や使用方法の観察といった言葉の情報以外の情報も収集できます。
調査対象者数に特別な決まりはなく、案件によりますが5名~20名くらいです。
どのようなときにヒアリング調査・インタビュー調査を利用するかですが、
①「まずどのような市場調査をしたらよいのかわからない」という最初のとっかかりに困っている状況の時には仮説を立てるためのヒントや、プロジェクトの方向性を見い出すヒントを収集するといった使い方
②アンケート調査の実施後、アンケート調査ではわからなかった詳しく知りたいところを、更に深掘りして詳しい顧客意識や行動を収集する使い方
といった使い方があります。
一般消費者向けの商品開発を例に挙げますと、市場調査の実施の際には通常は調査目的があり、仮説を立て、調査実施の順序としては「定量調査(アンケート調査)をして ⇒ 定性調査(グループインタビュー調査やデプスインタビュー調査)をする」といった順番が多いのですが、「調査目的はあるけれど、市場状況や顧客意識や行動がよくわからないので仮説が立てづらい」といったケースもあります。
そういった場合は、定量調査の実施前に、ターゲット顧客の意識や行動をざっくりと把握するためのヒアリング調査・インタビュー調査を実施し、「アイデア出し・仮説出し」をするといった使い方をします。「アイデア出し・仮説出し」とは、新規事業や新商品などのコンセプトを開発する前段階の作業です。(ヒアリング調査・インタビュー調査は1回ではなく、何度か実施する場合もあります)。
商品開発担当者は、現時点でご自身の頭の中にある情報から何らかの「仮説」を立て、その「仮説」について、想定しているターゲット消費者に受け入れられるのか、あるいはどのターゲット消費者に受け入れられるのか(買ってもらえるのか)といった仮説の検証を行うことと、、コンセプト作りに活用できるターゲット消費者の現状の行動や意識などについて、ヒアリング調査・インタビュー調査で収集します。ここで検証した仮説や収集した情報を基にして、コンセプト(製品・価格・売り場所・売り方・ネーミング・パッケージ等々)を作ります。
理想的にはこのあと何度かヒアリング調査・インタビュー調査をして、コンセプトを固めます。モノならば、販売しようとしている実物と変わらないようなものを作り、評価をしてもらいます。このとき、ネーミング、販売チャンネルなどマーケティング戦略に必要な情報も調査するのがよいです。
ヒアリング調査・インタビュー調査でコンセプトを固めたら、定量調査(アンケート調査)で仮説の検証を行います。ここでは「そのコンセプトはターゲットとする消費者(生活者)に受け入れられるか」、「市場性があるか(売れるか)」、「どのくらいの市場規模が見込めるか」、といったことを検証・調査します。
商品を発売した後は、発売直後、半年後、1年後など定期的にお客様満足不満足度調査など行い、市場に出した商品を次にどうしていけばいいのかを検討します。
商品を出した後にも、よりよいものに改善をしていき、そして1,2年たった段階で、商品に問題が出てきたとか、競合他社の製品が新しくマーケットに入ってきたという場合には、ヒアリング調査・インタビュー調査やアンケート調査を行って、再度、新しい商品のアイデア出しをしていく、というPDCAの循環の中で、調査を活用していくのが理想的な活用方法です。
上記の場合は「定性調査⇒定量調査⇒定性調査」の順序となっています。
意外によくある失敗例としてごご注意頂きたいのは、ターゲット消費者の現状把握調査を実施せずに、ご自身の頭の中の想像・思い込みだけで仮説を立てて(費用がかかる)アンケート調査をすぐに実施してしまうというケースです。このような思い込みで実施したアンケート調査結果をうのみにして商品開発やプロモーションを進めてしまうと、「発売したが全く売れない」という大惨事がのちに起こりますので、思い込みではなく顧客の現実を知るためのヒアリング調査・インタビュー調査の実施が有効です。
ヒアリング調査・インタビュー調査の活用の仕方のご紹介
ヒアリング調査・インタビュー調査は様々な場面で活用できる調査であり、「一般消費者(生活者)」 だけではなく、「企業の人」に対しても調査の実施が可能です。以下は活用方法のご紹介です。1.「取引先など企業の人」が調査対象(BtoB)の場合:
取引先顧客企業の満足度調査や、取引先ではない(全く関係がない)業界、今は取引がないが今後将来的に開拓をしていきたい業界についての情報収集をしたい場合などに、ヒアリング調査・インタビュー調査は有効です。特定の企業・業界の担当者に話を聴きに行きますので、二次データ(雑誌・書籍や既に世の中に出ている情報)では得られない貴重な情報が収集できます。
BtoB事例1:某容器メーカーが顧客企業の顧客満足度アンケート調査を実施するにあたり、調査項目を抽出するための事前調査に活用。
⇒取引先顧客企業の担当者が「自社の何に満足を感じているか、不満を感じているか?」は、自社の予想や思い込みとは違う場合が多いですので、アンケート調査の調査項目を抽出するために顧客企業へヒアリング調査・インタビュー調査を実施しました。アンケート調査は約500社に実施し、ヒアリング調査・インタビュー調査は10社に実施しました。
「自社の顧客企業」とひと口に言っても、その特徴によって「A社は○○については満足しているが、B社は不満がある」とか、「A社は●●についてはこうしたいと考えているが、C社はこうしたいと考えている」など、多種多様な評価をお持ちですので、まずは顧客企業を属性が共通するいくつかのグループに分類し、各グループから最低3社程度はヒアリング調査・インタビュー調査を実施して調査項目を抽出する必要があります。
どのようにグループ分けするかはその企業によってまちまちですが、全国に支店があり地域ごとに評価の違いがあるのではないか?という仮説がある場合は、「地域別」にグループ分けすると有効ですし、取引形態別に違いがあるのではないか?という仮説がある場合は、「直接取引しているメーカー、代理店経由のメーカー、卸売会社など取引形態別」にグループ分けしたり、あるいは取引金額により評価の違いがあるのではないか?という仮説がある場合は、取引金額の規模別に3~5グループに分けます。
グループ分けしたら、それぞれのグループの特徴を代表する企業(最低3社程度)にヒアリング調査・インタビュー調査をします。
この事例では、ヒアリング調査・インタビュー調査結果から、グループごとに違う特徴のあるご意見、共通するご意見など整理・分析し、アンケート調査質問を作成致しました。
アンケート調査は約500社の顧客企業に配布、調査結果を分析し、課題解決策をご提案しました。
BtoB事例2:某素材メーカーが現状の卸売会社を通しての下請け的販売だけでなく、販路拡大のためにユーザー企業(の業界)に直接売り込むにはどうしたらよいか、現状を把握するための調査に活用。
⇒『卸売会社を通しての販売は営業努力をしなくても売れるが、一方で卸売会社に価格などすべてをコントロールされている下請け状態のため、この現状を打開したい』という目的がありました。
しかしユーザー企業(の業界)への接点の持ち方や、ユーザー企業が商品についてどのような認識や評価を持っているか、情報収集はどのようにしているかなど、わからないことだらけの状態であり、まずは現状を把握する必要がありました。
このように接点がない調査対象者を抽出する場合は、ネットモニター会社を利用します。
当社が契約するネットモニター会社のモニターにスクリーニング調査を実施し、ユーザー企業(の業界)の発注担当者を7名抽出、ヒアリング調査・インタビュー調査を実施・調査結果を分析し、課題解決策をご提案しました。
2.「一般消費者(生活者)」が調査対象(BtoC)の場合:
一般消費者(生活者)に話を聴く調査はグループインタビュー調査(あるテーマのために集めた参加者5,6人に座談会形式で話をきくもの)の実施が多いですが、グループインタビュー調査のように座談会会場に集まってでは聴けない場合は、ヒアリング調査・インタビュー調査で実施します。
実施場所としては調査目的に合った場所になります。調査対象者のお宅や、趣味・スポーツ等の調査ならその話が聞きやすい場所といった具合です。
 理想を言えば、家の中で使う商品(例えば家電製品、洗剤などの日用品、調味料など様々なもの)について正確に現状把握をするためには、使っている場所で使っている状態をそのまま観察するのが最適です。
理想を言えば、家の中で使う商品(例えば家電製品、洗剤などの日用品、調味料など様々なもの)について正確に現状把握をするためには、使っている場所で使っている状態をそのまま観察するのが最適です。
というのも日常使っている商品は使い慣れているだけに無意識にやっている行動が多いため、グループインタビュー調査などで改めて「どういう使い方をしていますか?」と聴いたとしても、意識していることだけが話されて、無意識にやっていることは話としては出てきづらいからです。その「意識されずに話されていないところ」に重要なヒントが隠れていたりもしますので、それを観察も含めて調査するには普段使用している場所での調査が有効となります。
また、上記のような使用実態の観察だけでなく、その商品の置き場所がどこなのかによって、商品の形状を見直すヒントになったり、大型家電製品やトイレ、システムバスルームなど据え付けられている商品などは実際の状態についての評価を聴くためにもお宅に訪問してのヒアリング・撮影は非常に有効だといえます。
住宅設備メーカーのシステムバスルームの商品開発のケースでは、企業様の顧客リストから、購入年、商品タイプ・商品グレードなど条件に合う顧客をリストアップし、お宅に訪問、浴室の中での実際の使用行動や評価・感想を伺い、写真・動画撮影をし、浴室周りの状態から関連商品開発の種の情報、ライフスタイルについてのインタビューなどの情報を収集しました。
また競合住宅設備メーカーのユーザーについても調査対象としていたため、ネットモニター会社のモニターにスクリーニング調査を実施して条件に合うモニターを抽出し、同様の訪問ヒアリング調査・インタビュー調査を実施しました。
調査で収集した情報を分析し、商品コンセプト案をご提案致しました。

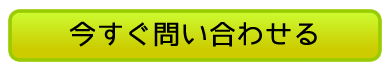
サービスについてのご不明点などございましたら、お電話での問い合わせも承っております。
電話に出られない場合は、ご用件を留守電に入れて頂ければ折り返しさせて頂きます。
0745-53-8006 までお願いいたします。
■ヒアリング調査・インタビュー調査の、お申し込みから納品までの流れ
1 サービスについてのご不明点などは、まずお気軽に問い合わせフォームまたはお電話でお問合せ下さい。
電話番号:0745-53-8006
2 お申し込み
問い合わせフォームまたはお電話で、お申込みの旨をご連絡下さい。
3 ヒアリング
お電話でヒアリング調査・インタビュー調査の設計に必要な情報(調査目的や御社の課題・現状・将来目的など)をヒアリングさせていただきます。
4 インタビュー質問項目を作成
当社でインタビュー質問項目案を作成、御社のご担当者と修正などやり取りをし、インタビュー質問項目を完成させます。
5 調査対象者を抽出
調査対象者の抽出方法は2つに分かれます。
①御社関連で調査対象者を抽出する方法:
御社が保有する顧客リストの中から、調査対象者の条件に合うお客様を選んで調査を依頼する(御社が直接依頼、または当社が依頼を代行します) (例:御社のシステムバスルームを契約したお客様リストの中から抽出する)
②ネットモニターの中から調査対象者を抽出する方法:
当社が契約するネットモニター会社のモニターにスクリーニング調査を実施し、調査対象者の条件にあるモニターを抽出する(スクリーニング調査費用が発生します)
6 ヒアリング調査・インタビュー調査を実施
調査対象者にアポ取りをし、60~90分程度お話を伺います。
調査の実施は、インタビューに適したリラックスできる落ち着いた場所や、調査課題に応じた場所で行います。例えばシステムバスルームの商品開発なら、調査対象者のお宅に伺って、バスルームとその周辺・関連設備などの実際の使用行動・評価・感想やライフスタイルなど、必要な情報をインタビューするといったように、最適な調査方法をご提案致します。
7 ヒアリング調査・インタビュー調査のまとめ資料を作成
インタビューした内容を、質問項目別にわかりやすく整理した資料を作成致します。写真や動画がある場合、それも添付致します。
8 課題解決策のご提案報告書を作成
調査目的・御社の課題を念頭に置き、調査結果から当社が発想した課題解決策を報告書にご提案としてまとめます。
9 ご納品
メールで、上記7、8で作成したファイルをお送り致します。
■ヒアリング調査・インタビュー調査を安く実施する方法としては、今まで市場調査会社に外注していたものを「自社内で実施できるスタッフを養成する」という方法もあります。
当社では、今までヒアリング調査・インタビュー調査を自社内で実施したことのない企業様に、やり方をお教えする以下の2つのサービスを提供しております。
「ヒアリング調査・インタビュー調査ってどうやるの?」「準備はどうするの?」など、具体的・ていねいに一から十までお教え致します。
サービス内容の詳細は以下のページをご覧下さい。
①ヒアリング調査・インタビュー調査のZoomオンライン講座・・・・・Zoomを使っての3名までの講座です。
②ヒアリング調査・インタビュー調査の訪問研修・・・・・御社にご訪問して研修致します。
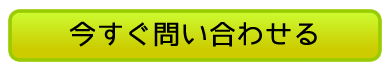
サービスについてのご不明点などございましたら、お電話での問い合わせも承っております。
電話に出られない場合は、ご用件を留守電に入れて頂ければ折り返しさせて頂きます。
0745-53-8006 までお願いいたします。
