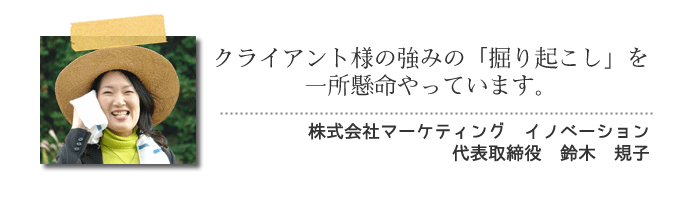ごあいさつ
 当社サイトにご訪問いただき、まことにありがとうございます。株式会社マーケティング イノベーション代表取締役の鈴木規子と申します。「マーケティングはイノベーション《革新》だ」との思いから、そのまんまですが、社名にいたしました。私は1962年生まれで、マーケティング会社、シンクタンク、広告代理店での20余年のマーケティング業務を経て、2004年3月に会社を設立いたしました。会社員時代の実績(じまんばなし)を一つ紹介させて頂きますと、マーケティング会社勤務時に家電メーカーさんを担当した際、女性向けの新商品開発という課題でアンケート調査とグループインタビュー調査を実施し、調査結果から提案した美容家電の新商品コンセプトが採用され(2商品)、今でも売れ続けているロングセラー商品となっています。この時の調査でもそうだったのですが、新商品開発での市場調査のポイントは、消費者(生活者)の客観的な現状(ファクト)を丁寧にくみ上げる(定量的にも定性的にも)ことが重要で、その情報を頭の中で昇華しアイデアにアウトプットするのはマーケターのセンスや経験などであると考えています。
当社サイトにご訪問いただき、まことにありがとうございます。株式会社マーケティング イノベーション代表取締役の鈴木規子と申します。「マーケティングはイノベーション《革新》だ」との思いから、そのまんまですが、社名にいたしました。私は1962年生まれで、マーケティング会社、シンクタンク、広告代理店での20余年のマーケティング業務を経て、2004年3月に会社を設立いたしました。会社員時代の実績(じまんばなし)を一つ紹介させて頂きますと、マーケティング会社勤務時に家電メーカーさんを担当した際、女性向けの新商品開発という課題でアンケート調査とグループインタビュー調査を実施し、調査結果から提案した美容家電の新商品コンセプトが採用され(2商品)、今でも売れ続けているロングセラー商品となっています。この時の調査でもそうだったのですが、新商品開発での市場調査のポイントは、消費者(生活者)の客観的な現状(ファクト)を丁寧にくみ上げる(定量的にも定性的にも)ことが重要で、その情報を頭の中で昇華しアイデアにアウトプットするのはマーケターのセンスや経験などであると考えています。
●会社設立のきっかけ。
2000年頃、資格試験取得の勉強をしておりましたときに、中小企業が日本の企業の99%以上を占めることや、マーケティングが活用されていないこと、日本経済の活性化には中小企業の活性化が肝心なことを知り、根が非常に単純なもので、急に「私がやらねば誰がやる!」と思い立った次第です。
当時は漠然と「自分のマーケティングスキルをいつか役立てよう。」と考えていただけだったのですが、その後機会もあり、奈良で開業し現在に至っています。
会社を設立してから中小企業経営者の方の話を伺うようになって、マーケティングが活用されていないことを実際の話として知り、マーケティングを身近に取り入れていただくべく、当社でご提供するサービスも「これはうちの会社で利用できるかもしれない。」と気付いていただけるよう、いろいろなサービスをご用意しています。
●生活者と企業の橋渡し役に。
マーケティング会社の役割のひとつは≪生活者と企業の橋渡し役≫だと私は考えています。
生活者の不満や不安、欲求など、形になってはいない意識をマーケティング会社がていねいに拾ってコンセプトや企画にし、それを企業様に具体的な商品やサービスにしていただいたり、企業様の良さを伝えたり、誤解が生じてマイナス評価になっているものを解消して共感を得られるようにしたり、生活者と企業様のあいだにあって双方の満足の向上に役立てればと思うのです。
≪橋渡し役≫とも似ていますが、当社は≪埋もれているものの発掘≫も注力しています。いいものを持っておられるのに十分に発揮できていない企業やお店の≪いいところ≫を発見して、お客様に買っていただけるようにすることや、今はまだ顕在化していない生活者の欲求を見つけ出して商品やサービスに具現化すること、あるいは結婚後、家庭に入って能力に見合った仕事が見つかりにくい女性の活躍の場を提供すること、などです。
●当社がお手伝いしたいのは、《とことん本気で》経営革新に取り組まれるクライアント様です。
 私がこの《本気さ》の重要性を実感したのは、10年以上前に取り組んだある仕事がきっかけでした。
私がこの《本気さ》の重要性を実感したのは、10年以上前に取り組んだある仕事がきっかけでした。
それは大手企業様の仕事で、その企業が地方へ進出する際に、「地元の人たちとうまく共生するための方策」を調査する、というものです。それで私は日本各地に行き、「外からやってきたけれども、地元の人から認められ地元に溶け込んでいる企業」がどのようなことを実施しているのかを詳細に調査しました。
そして分析のために共生の実施内容を分類し、成功の要因を突き詰めて考えてみますと、一番重要な核となる要因は《目的のために本気で取り組むリーダーが、ひとりでも存在する》ということに行きつきました。
クライアントからは「地元と共生する手法」の提案を求められていましたので、そのような精神論を報告書に記載するのはどうかとも躊躇しましたが、実際的な地元とうまくやる手法・メニューを報告するだけではなく、《本気のリーダーいること》が必須条件であることははずせないな、と考えて、ちょっと異質な内容でしたがしっかりと入れておきました(笑)。
当社はノウハウやスキルを提供する立場ですので、矛盾することを申し上げるようですが、ノウハウよりも《本気で取り組むことが何より重要》ということも、その仕事をきっかけに思いを強くした次第です。
ですので≪本気の経営者様≫にノウハウをプラスすれば、まさに《鬼に金棒》ではないでしょうか?
このような思いがありますので、当社は「お客さまに喜ばれるサービスを提供したい!」「お客さまの不満を解決する商品を作りたい!」と、≪本気で≫考えて取り組まれている企業様の、マーケティング力の向上のサポートを、全力でさせていただきたいと考えています。
一緒にやっていきましょう!
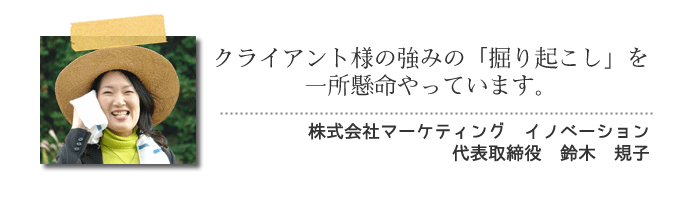
●「私もいつも≪本気≫でやってます。」ということで(笑)
プライベートで私が本気で取り組んだ仕事をひとつ。
私が現在住んでいるマンションの管理組合の話です。
1999年10月に当時で築10年くらいの中古マンションを購入しました。管理組合の理事は輪番制だとのことで、2001年11月から1年間、管理組合理事会の理事になりました。
理事の仕事は何かもわからないまま、1回目の理事会に出席しました。
マンションの管理を請け負う管理会社の人が会議を取り仕切り、そのうち前期の理事会から引継ぎ案件の、敷地の修繕工事の見積りについての説明になりました。
そこで私は「工事費用のあい見積りを取ってないんですか?」と、ごく自然なギモンとして軽く、管理会社の人に尋ねました。
すると「あい見積りを取る必要はないんです!いつもこの業者でやっています!」と、驚くようなこわばったリアクションに一瞬ひるみましたが、アイミツを取らないのはおかしいので、「あい見積りは必ず取るようにしてくださいね。」と依頼しました。
すると、また「いつもこの業者でやっている、なんだかんだ」と言うので、これは妙だ!と思いつつ、「とにかくあい見積もりを取ってくださいね!」と言い、理事長にも賛成するよう話を向け、その後1回目の理事会は終了しました。
それから私は家でインターネットで情報収集したり、ビジネス誌や書籍を購入したりして、管理組合や管理会社の情報を片っ端から収集し、本来は管理組合理事会が主体であり、管理会社は決定に従い実施していく立場であること(その当時は管理会社が主体だった)、当マンションの管理会社がどうも悪質な部類であり、管理費を不当に高額に取っていること(330戸あるので、それまでの約10年間に約10億円ほど)、住民がひと月に払う費用の内訳として、管理費が高く(約13,000円くらい)、修繕積立金が非常に少なく(約3,000円くらい)、このままでは大規模修繕工事の出費に耐えられないこと、を知りました。
情報を収集すればするほど、「このままでは大変だ!」といてもたってもいられなくなり、2回目の理事会のあと、理事長以下理事会の役員全員(8~9人くらい)の家を回って、それまでに収集した管理会社などの資料や、周辺マンションの管理費と修繕積立金と当マンションとの比較表を渡して説明しながら、「この管理会社はまずいので、何とかしないといけない、管理会社を替えないといけないと思わないですか?」という話をしました。
ところが皆さんの反応は想定外のものでした(泣)。
「問題だと思うけど、管理会社を替えるなんて無理ですわ。」や、「私はできない。誰かがやってくれたらと思いますが。」とか「今の管理会社もそこそこやってくれてますしね(日常業務をやる管理員は親切だった)。替えることまでする必要あるでしょうか。」などで、ひとりも管理会社を替えることに賛成してくれなかったのです。
「理事の人たちは当然管理会社変更に賛成してくれ、理事長さんあたりか、理事長はけっこうご高齢だったので、3,40代の男性も6,7人おられるので、誰かが主になって進めてくれるはず。」と安易に考えていた私は、「いったいどうしたらいいんやろう・・・。」と途方にくれてしまいました。
それからもずっと、どうやったらよいかを考えていましたが妙案は浮かばず、その期の管理組合最後の仕事である総会が10月に開催されました。
総会というのは、ほとんどの住民は関心がないので委任状を出し、参加するのは330戸中だいたい毎年10人くらいです。
議案の説明と採決を進めるなかで、参加者のなかで3人の人が、いろいろ質問したり、苦情を言っているのを聞いているうちに、「そうだ、この人たちは問題意識が高そうだし、一緒に管理会社変更に動いてくれないかな?」と思いつきました。
それで、部屋番号と名前をメモし、総会後家に帰ってすぐに、手紙を書きました。
「今の管理会社の現状や、管理費、修繕積立金などの説明と、管理会社の変更すべきなので、一緒にやってくれませんか?」という内容です。
すると、ありがたいことに3人の方は快く応じてくれて、それから1年間、毎月2,3回定期的に会合し、コンペにかける管理会社の資料や裏づけ資料を集めて検討し、実際に管理物件の視察などもし、管理組合理事会にかけて、議案としてとりあげ決定してもらうまでを段取りしました。
そして確実に管理会社変更を成し遂げるには、事情をよくわかった人が理事にならなければ、現管理会社の人に影響を受けてこの計画が頓挫するかもしれない、ということになり、私が理事長に立候補しもう一人が理事に立候補して、理事となりました。それが2003年の11月のことです。
私たち2人が理事になったことで、管理組合を牛耳っていた管理会社社員幹部は、もう確実に替えられるとわかっているので重要な資料を出さなかったり、問題をそのままにしたりといやがらせをしてきました。
また住民の中のコワイ系列の人が「ウチの関連会社を業者に使ってくれ。」とねじこんできたり(お断りしました)、と管理会社を変更するまでに紆余曲折がありましたが、なんとか2004年の2月頃(?)、臨時総会を経て無事管理会社を変更することができました。
ところでこの混乱のさ中、2004年3月に私は会社を設立したのですが、理事長になったことで、この年は結局10月いっぱいまで開店休業状態となってしまいました。
といいますのは、管理会社を変更したのは一安心だったのですが、重要な書類の引継ぎができていない、業務が混乱する、理事会の運営を根本から改革するなど理事長業務を朝から晩まで、一週間休みなしで毎日やる必要が起こってきたからです。(もちろん無給ですよ(^_^)。逆にいろいろと自腹で支払っていました。)
更に、1回目の大規模修繕工事の実施年になっており、2004年の6月から10月まで工事も監理していました。
施工の建設会社はコンペにし、足場を組まずにゴンドラにするということと、大手ゼネコンだということでT社が選ばれたのですが、このT社が、私の理事長業務を更に超過酷なものとしてくれました(涙)。
T社はコンペで示した仕様をいくつも反故にしたのです。
大きなところでは、ゴンドラが決め手のひとつであったにもかかわらず、ゴンドラは無理だといい、足場を組むことになった、というようなことです。
施工は手抜き工事の連続で監理がまったくできておらず、こちらが目を光らせてチェックしていないとすぐにむちゃくちゃな施工をやるような会社だったのです。
あとでゼネコンに勤めている住民の人に聞くと、「超大手といっても大規模修繕工事などは二軍の人材が来ることが多い」とのことなんですと・・・。
夏の暑い間、建物の足場を伝って、1階から7階まで一軒一軒のベランダに入らせていただいてチェックしたり、外壁をチェックしたりと「とび職さん」状態です(疲)。
あまりにひどいので、ずさん施工の数々をビデオに録画し、工事の終盤はT社の上部管理職との交渉で「施工不良で裁判に訴える」という話もしていたのですが、訴えるためには当方で裁判に勝つだけの資料を準備しなければならず、ボランティアでそれだけのことをできる人がいない、ということで結局泣き寝入りしました。
・・・そんなこんなで、2001年にたまたま理事の順番が回ってきたことで、ある意味ドツボにはまったようにも見える私ですが(親には「会社作ったのに何してるの!早く仕事しなさい!」とチクチク言われる始末で・・。)、この期間にマンション内に仲の良い知人もできましたし、たくさんの方から「ありがとう」と言っていただけましたし、管理会社を変更したことで、管理費と修繕積立金の比率がおおよそ逆転し、ものすごく管理費が下がり、将来の修繕積立金も少しは安心できるようになりました。
そして2004年11月に管理組合理事長の任期を終えた後、マンションのコミュニティを醸成するため、今度は『コミュニティ専門委員会』という管理組合の下部組織を立ち上げました。
当マンションは330戸の大規模マンションで、売却が多く将来的にはスラム化や賃貸物件が増えるといった危惧を私は持っていました。
住民がずっと住み続けていくポイントは何かと考えると、それは「管理」と「コミュニティ」だと考えられます。
「管理」とは「マンションのインフラ」といえるすべてのことで、現在管理会社へ委託している事柄(たとえば管理員、点検業務、植栽など)のそれぞれや、建物・設備がきちんとメンテナンスされている、バリアフリーになっている、といったことなどです。
一方「コミュニティ」はメンタルな面での、「ここに住みたい、ここから離れたくない」という気持ちにされるもの・・・「安心、楽しく、住みやすい、居心地がいい」とか「孤独な老人をつくらない」「子供たちをコミュニティでしつけする」など、現代版の「長屋のよさ」的なものだといえます。コミュニティ意識が醸成されていくと、ひとりよがりな意見を言う人が減ってきたり、人の目があるので自分勝手な行動(例えばゴミ捨て場所に捨ててはいけないものを捨てる行為など)も減ってくることが実証されています。
コミュニティ意識は急には醸成されないものであり、またこのような大規模マンションでは自然に醸成されていくものではないので、専門委員会で長期的に検討と実施をしていきたいと考えたのです。
マンションはひとつの密な地域社会ですので、この中で、住民それぞれが持っていく得意なこと、智恵、ノウハウなどを出し合ったり、助け合ったりすることや、ずっとこのマンションに住み続けたいと思えるようにしていければと思っています。
管理会社変更については、当初まったく自分でやる気はなかったのですが、誰もやってくれそうもないので、≪本気を出して≫やった、というおはなしでした。
長文にお付き合いいただき、ありがとうございましたm(_ _)m。
この間、何度も繰り返し思ったのは≪隗より始めよ≫という中国の格言です(三省堂の国語辞典によると「言い出した人から始めなさい」とあります)。
自分が管理会社を替えるべきだと思ったなら、自分でやるべきであり、「誰かがやってくれたらいいのに。」と待っていてはいけないんだ、ということを強烈に学びました。
この言葉は今も、私の座右の銘にしています。

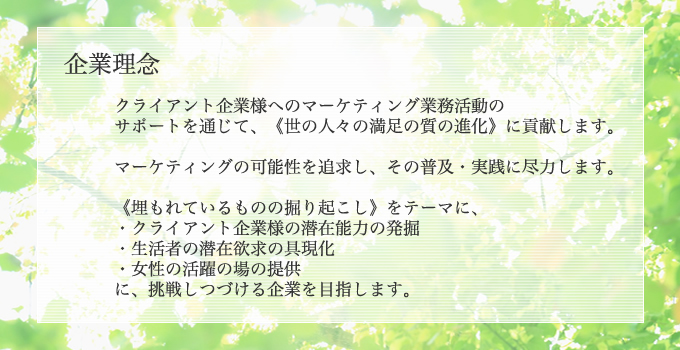

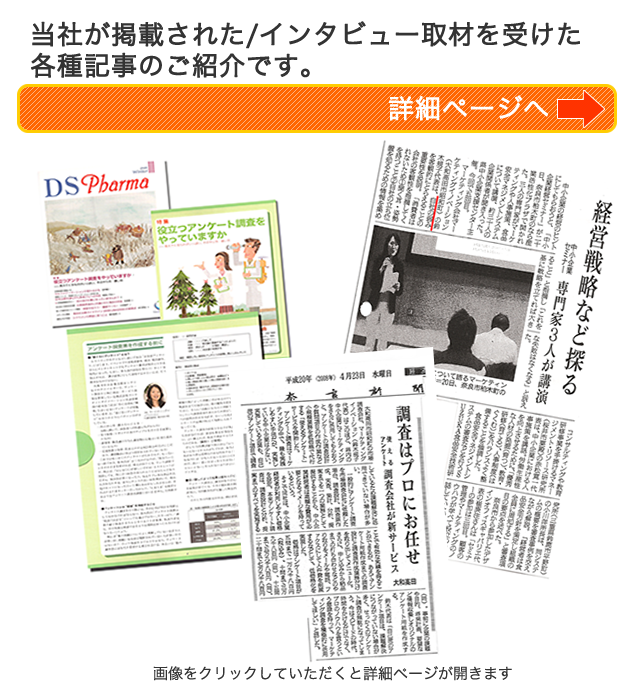
 当社サイトにご訪問いただき、まことにありがとうございます。株式会社マーケティング イノベーション代表取締役の鈴木規子と申します。「マーケティングはイノベーション《革新》だ」との思いから、そのまんまですが、社名にいたしました。私は1962年生まれで、マーケティング会社、シンクタンク、広告代理店での20余年のマーケティング業務を経て、2004年3月に会社を設立いたしました。会社員時代の実績(じまんばなし)を一つ紹介させて頂きますと、マーケティング会社勤務時に家電メーカーさんを担当した際、女性向けの新商品開発という課題でアンケート調査とグループインタビュー調査を実施し、調査結果から提案した美容家電の新商品コンセプトが採用され(2商品)、今でも売れ続けているロングセラー商品となっています。この時の調査でもそうだったのですが、新商品開発での市場調査のポイントは、消費者(生活者)の客観的な現状(ファクト)を丁寧にくみ上げる(定量的にも定性的にも)ことが重要で、その情報を頭の中で昇華しアイデアにアウトプットするのはマーケターのセンスや経験などであると考えています。
当社サイトにご訪問いただき、まことにありがとうございます。株式会社マーケティング イノベーション代表取締役の鈴木規子と申します。「マーケティングはイノベーション《革新》だ」との思いから、そのまんまですが、社名にいたしました。私は1962年生まれで、マーケティング会社、シンクタンク、広告代理店での20余年のマーケティング業務を経て、2004年3月に会社を設立いたしました。会社員時代の実績(じまんばなし)を一つ紹介させて頂きますと、マーケティング会社勤務時に家電メーカーさんを担当した際、女性向けの新商品開発という課題でアンケート調査とグループインタビュー調査を実施し、調査結果から提案した美容家電の新商品コンセプトが採用され(2商品)、今でも売れ続けているロングセラー商品となっています。この時の調査でもそうだったのですが、新商品開発での市場調査のポイントは、消費者(生活者)の客観的な現状(ファクト)を丁寧にくみ上げる(定量的にも定性的にも)ことが重要で、その情報を頭の中で昇華しアイデアにアウトプットするのはマーケターのセンスや経験などであると考えています。 私がこの《本気さ》の重要性を実感したのは、10年以上前に取り組んだある仕事がきっかけでした。
私がこの《本気さ》の重要性を実感したのは、10年以上前に取り組んだある仕事がきっかけでした。